2018/05/15

みなさん、学んだことを上手にアウトプットできてます?
私はインプットしては忘れ、インプットしては忘れの繰り返しです。
うまくアウトプットして習慣化する方法ないかなと考えていたのですが、NHKの100分で名著の「宮本武蔵 五輪書」を見て、ある意味少し霧がはれたような気がしました。
文明は進化しても、結局、今も昔も、人間の本質は変わらないのだ。
五輪書が書かれた背景
豊臣の時代から大阪の陣を経て徳川幕府が治める平和な時代となり、戦国時代を経験した武蔵が、平和ボケしている武士達を見て、このままでは良くないと感じたようです。
素浪人時代60回以上の勝負に挑み負けなし、吉岡一門を破り、世の中に名を知らした武蔵が、これまで自分の歩んだ人生を振り返り、これまで学んだ事をまとめ、後世の武士へ託した兵法です。
今で言うと、戦争を知らない若者たちへの警鐘と言ったところでしょうか。
現代も、本当に平和な世の中なのか?と問われれば、
現実は格差社会、ちょっとした歯車も掛け違いで、一度底に落ちると這い上がるには相当な努力が必要となります。
結局、この世の中は、競争社会、弱肉強食、常に勝負と思い勝ち続けなければならないのは同じではないでしょうか。
これまで、武蔵は無頼な天外孤独の素浪人のイメージがありましたが、人生の後半はそうではなかったようです。
大阪夏の陣以降、大名に客分として迎えられ、武芸以外の様々な分野でも才能を発揮しました。
そして、武蔵は、、、
「兵法の道で会得した道理によって他の様々な芸能の道を行っているので、全てにおいて、私に師匠はいない」と説いています。
兵法の道を究めれば、すべての道に通じる。
昔、書かれた五輪書が、現代に通じるなと感じたところは、
今も昔も人間の本質は変わらない!
最近の多くのビジネス本に書かれているような攻略法なんてない。
そう! きれいごとでは行かないのだと感じさせるところです。
そして、先ずは、組織より、個としての道を探求し、個としての自分を鍛錬した結果が、全ての道に通じる。
そして組織にも貢献できる。
スティーブン・R・コビーの七つの習慣で言うと第1から3の習慣「私的成功のための習慣」に通じるところですし、後に記載する、「兵法の道を学ぶ心がけ(9条)」は、ミッション・ステートメントのヒントに持ってこいと思います。
それでは、五輪書をざっくり説明していきます。
五輪書の構成は、地・水・火・風・空の五巻から成り立っています。
地の巻(正しい道の地盤を固める)
水の巻(鍛錬の方法)
火の巻(戦術)
風の巻(他の流派の欠点)
空の巻(本質としての「空」)
地の巻(正しい道の地盤を固める)
世の中には武士以外にも士農工商と様々な職業があります。それらには、それぞれの道がる。
武蔵は武士以外の職業を見下していた訳ではありません。
例えば農の道、商の道と説明したうえで、士農工商の位置付けを農・商・士・工の順で紹介し武士の上に農民と商人が、記載されており、武蔵の身分の位置づけは常識とは違っていたようです。
これを踏まえたうえで・・
1 武士が兵法を行う道は、何事においても人より優れていることを根本として、一人で行う切り合いに勝ち、数人との戦いに勝ち、主君のため、自分のために名を上げ、身を立てようと思うことであり、これも兵法の優れた力によって得られるものである。
2 「実践で役に立つこと」を第一に考えなければならない。
3 「様々な武具の利を知ること」、適材適所で使いこなせ、但し、基本は太刀である。太刀は昔から武士のもっとも基本とする武具で、世を治める武士のシンボルであり、かつ常に身に帯びる武士の象徴である。武士であれば、多くの武具を使いこなさなければならない、しかし、一番の基本となるものはやはり太刀である。
4 「兵法の道を学ぶ心がけ(9条)」
- よこしまな事を考えないこと
- 自分の道の鍛錬をすること
- 諸芸に触れてみること
- 諸職の道も知ること
- 物事の損得をわきまえること
- 自分の目でみて、本物と偽者を見分けること
- 目に見えぬところを悟って知ること
- わずかなっことも気をつけること
- 役に立たないことをしないこと
①~⑧までを実行し理解たうえでの、⑨の「役に立たないことをしないこと」である。
5 心に兵法を絶やさず、正しい道を勤めていけば、世の中のあらゆる物事に勝つことができる。いずれの道においても人に負けないところを知って、身を立て、名を上げるのが兵法の道
水の巻(剣術の鍛錬法)
剣術は兵法の核であり、様々な応用方法がある。そのありようは、器によって形を変え、一滴ともなり大海ともなる水。
これを踏まえたうえで・・・・
1 個の書で説いていることを自分自身が見出したこととして、試して、その技とからだの感触を知り、様々試して、自分でよく考えて、工夫して繰り返しやる。読むだけで満足してはいけない。自分のからだで確かめて初めてどういうことか分かる。
2 剣術の技の基礎は、「心持」、「姿勢」、「目の付け方」の3つ
① 「心持」とは、心を広くまっすぐにして強く引っ張らず、少しもたるむことなく、心が偏らないように、心を真ん中において、心を静かにゆるがせて、その心の刹那も揺るぎやまないように、よくよく吟味すべきである。
② 「姿勢」は、顔はうつむかず傾かず、歪まず、目を乱さず、額に皺を寄せず、眉の間に皺をよせ、目の玉を動かさず、瞬きをしないように思って、目を少しすくめるようにして、周りを広く見るようにする。
③ 「目の付け方」とは、観(大きく見ること)・見(一点を見ること)二つの目があり、観の目を強く、見の目を弱く、遠いところを近いように見、遠いところを近いように見ることが兵法では必要不可欠である。敵の太刀の位置を知っているが、少しも敵の太刀を見ないことが、兵法では大事である。
3 「太刀の道をしる」こと、剣術に必殺技などはない。同じ動きであっても僅かな違いに敏感になることにより、太刀の道がおのずと分かるような感覚を研ぎ澄ます。太刀の道が分かれば敵の動きも見て取れるようになり、次の手も予測できるようになる、敵の一振りを見ただけで敵の力量が分かる。
4 「有構無構のおしえ」とは、形の基本を熟知すれば、その形は基本を踏まえたうえで、どうのようにでも変化する。そうであるから構えはあるが、構えはない。
5 敵と打ち合う時の工夫しろ。敵の拍子(リズム)の逆をとって打つ
「一拍子の打」とは、ゆっくりとしてた敵には自分の方から早く打つ
「二の越の打」とは、気の早い敵には、自分が打つと見せかけて、相手が打ってきたところをかわして打つ
「無念無想の打」とは、敵も自分も打とうとすると時、打つ気配を見せず強く打つ
6 「鍛錬の心構え」は、絶えず鍛錬を心掛け、急ぐ心なく、得を得て、その心を知って、千里の道も一歩ずつ歩んでいく。ゆったりと考え、この兵法を鍛錬することは「武士の役目」だと心得て、今日は昨日の我に勝ち、明日は下手に勝ち、あとは上手に勝つと思って、少しも脇の道に心がいかないように思うべきである。毎日の稽古を続けてこそ鍛錬と言えるのである。よくよく吟味あるべきである。
火の巻(戦術、小さな火でも燃え上がれば、大火となる。)
1 「戦いの場を見分けろ。」一人で多数を相手とする時は、広場で戦うより、障害物の多い森の中、田んぼのあぜ道、敵を「魚つなぎ」にして打つなど、その時々臨機応変に対応する。
2「枕をおさえる」とは、敵に戦わずして勝つ。
「敵を知ること」、すなわち、我が身を敵になり替わって考えてみるこ
「敵の強みを消す」とは、戦う前に敵をよく知ること、研究すること。
勝つためにあらゆる手を尽くし、敵を崩し、敵が打つ前に「う」の字も出ないうちに頭を押さえて後をさせない。
風の巻(他の流派の欠点をしる)
敵を研究し、敵の誤りをよく知ることで自分の正しい道理を確認せよ。
空の巻(本質としての「空」を目指す)
1 空とは、物事のないところ、未だ知ることができない所を「空」と見立て、道に少しも暗くなく、心に迷いなく、毎朝毎時に怠ることなく、心意二つの心を磨き、観見二つの目を研いで、少しも曇りなく迷いの雲の晴れたところこそ、真実の空と知るべきである。
2 真実の道に達しないうちは、自分では確かな道だと思っても、良いことだと思っていても、冷静に心を正しくして、世の中の大法に合わせてみれば。自分のひいきの心、歪んだ眼によって、正しい道から外れているものである。
そうしたところを知って、正しいところを本とし、真実の心を道として、正しく大いなるところを思い取って、空を道とし、道を空と見るのである。
3 道理を会得すれば、もはや道理にとらわれず、兵法の道に自然と自由があって、いつのまにか不思議な力を得て、その時々に相応して拍子(リズム)を知り、意識しないでも自然に打てば、自然と当たる。是はみな空の道である。
まとめ
確かに、現代の社会に適合させるには、抽象的な部分を多く、読み替えが必要だったり、自分なりによく考えて試行錯誤しなければならない書物です。
でも私には・・・
それはたぶん、書いた人物が同じ日本人だからでしょう。日本特有の道徳的な考え方や、昔からある武士道的なものが、自然と心に入ってきたのだと思います。
これまで読んだ本は、原作が海外だったり、現代の人物が書いているもので、内容がスマートで読みやすく理解できるのですが、それを実践できるかと言えば、私はできていない。
最近の本のタイトルには、「無理せずできる。」とか「習慣化して」とか、なんかすぐ実践できそうに書いてある。でも、できていない。
振り返ってみると私の数少ない成功体験は、自分自身の信じたことを脇を見ないようにして、自分の欲を抑え、たまには自分の至らなさから他人に迷惑をかけ、成功するか分からない事柄を信じて、ひたすら行うことで、なしえたと言う体験でした。
しかし、私は何でも根性論や精神論でかたずけるのが嫌で、最近の話題のビジネス本を読んできたのですが、なぜか、五輪書のような・・・・・根性・精神論がしっくりくるようです。
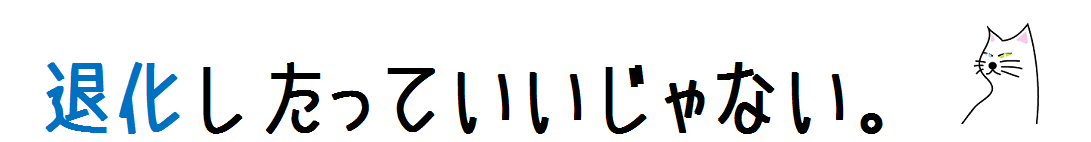



-1627100_1280-290x202.jpg)


-2100871_1280-290x203.jpg)

-2354962_1280-290x204.jpg)
-2318998_1280-290x200.jpg)

-1807497_1920-290x203.jpg)

-185435_1280-290x204.jpg)
-1729274_1280-290x203.jpg)
-2179243_1920-290x204.jpg)



